こんにちは、ちょこきなこです。
「妖怪ウォッチ ゲラポリズム」やってて思ったのが、よくあるアプリのゲームと異なる点がいくつかあったので、気付いた点をまとめてみました。
具体的には以下の場面です。
1:せってい画面に「ヘルプ」と「遊び方」がある
せってい画面に「ヘルプ」と「遊び方」の項目が並んでいます。



ソシャゲに慣れてるとヘルプと遊び方はほぼ同一の内容を指していることが多いです。いくつか見てみます。
1つめ。欅坂46の場合。ヘルプの中に内包されていました。

一番下に権利表記の項目があります。

2つめ。メギド72の場合。ヘルプと各種規約で分かれています。


3つめ。リンクスリングスの場合。ヘルプと各種情報でした。





5つめ。ドクターマリオワールドは「チュートリアル」でした。なるほど。


6つめ。とあるはヘルプ


7つめ。妖怪ウォッチつながりで、メダルウォーズはヘルプ。

開くと「妖怪ウキウキペディア」となってます。

8つめ。妖怪三国志はヘルプと遊び方の項目が離れた場所にありました。

ヘルプはブラウザが起動して、よくある質問に飛ばされます。

遊び方はゲームのルールでした。


もしかしたら妖怪ウォッチシリーズだとメンタルモデルとしては成立するのかな…?
逆にそれ以外だと見かけなかったので、やはりヘルプと遊び方の項目を用意するのは一般的ではないのかもしれません。
2:お知らせ機能が実装されていなかった
リリース時点でお知らせ機能が実装されていなかった、というのも興味深いです。
リリース後のバージョン1.0.4で実装されていました。



タイミング的にはリリースしてから一ヶ月後の実装です。ちなみにそれまでは公式サイトで告知していたみたいです。

運用しない前提のカジュアルゲームならストアの更新履歴だけでも足りるとは思いますが、この規模のアプリでお知らせ機能がないと後々運営側が不便に感じそうなものだけど…。思い切った判断をしたなと思いました。
有名IPですし、コンテンツに対する期待感もあるので、ユーザーからすると「イベントやキャンペーンとかしないのかな」と不安に感じる部分もあると予想されます。
3:ボタンが小さい
これはコンシューマのデザイナーが陥りがちですが、タップ範囲のイメージが直感的に分からず、各種情報を詰めすぎて結果的に文字やボタンなどの要素の面積が狭くなる傾向があります。
特に楽曲選択画面でその特徴が顕著に現れていました。

使用頻度の低いボタンは小さくても良いですが、あまりに小さいと押したいと思った瞬間に押しづらそうだと感じるため、限度があります。
人によって指の大きさが異なるので、個人差はありますが1cm四方が目安です。
(もしかしてメインターゲットは低年齢だからボタンサイズは小さくても良いと思ったのかも…?)
4:育成が「もちもの」ラベル
キャラを育成するための機能のラベルが「もちもの」となっています。

強化素材以外のアイテムも表示されるのであれば「もちもの」で良いのですが、現状では強化素材以外に表示されるものがなく、この画面で行えることは強化しかありません。

なので「もちもの」より「育成」や「強化」といったラベルを使用する方がソシャゲとして分かりやすくなるのかな、と思いました。
もしかしたらコンシューマ版だと「もちもの」から妖怪を育成するのが一般的な設計なのかな…?
あるいは年齢層が低いので「強化」という言葉を使えなかった、とか?
いずれにしろ思考停止になっていないのは良いのですが、ソシャゲの暗黙知の部分を無理に変えてしまうとメンタルモデルが機能せず、学習コストの手間やストレスに感じる部分が生まれてしまうので、注意が必要になります。
5:ボタンの色が多すぎる
1:肯定、進むときに使われるカラー
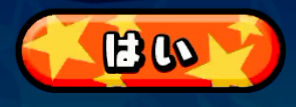
2:否定、戻るときに使われるカラー

3:その画面の補足情報や下位階層などに使われるカラー

4:その画面内での便利機能。フィルタなど

5:チェックボックスON/OFF

6:難易度三段階(かんたん、ふつう、むずかしい)



このタイトルのターゲットは年齢層低めなので、ボタンに限らず全体的に色が多いです。また、運用をしないと割り切れば、情報がこれ以上増えることもないので、割と意図的にやっている気がしました。
通常は運用を見越して情報を増やすことには慎重になりがちです。
今回の場合は運用をしないこと、またターゲットの年齢層が低いとすれば色がたくさんあっても良いのかも。
恐らく成人と比較して情報の精査に時間がかかるので観察すること、情報量の多さによるストレスはなく、逆に分かりやすさを優先しシンプルな画面にすると分かりやすさよりも地味で面白くなさそう、が優位に立つのかな…。
でも必ずしもそういうわけでもないし…GBなんかモノクロでも売れてたしな…あくまで選択肢として色数は多く使っても許容される、というだけで色数を多くしなければならない、というわけではないのかな…。
この辺はちょっとちゃんと調べてみても良いのかもしれない…。
まとめ
いくつかソシャゲっぽくない実装を挙げてみました。
1:ヘルプと遊び方の混在
2:お知らせ機能をリリース後に実装
3:ボタンサイズが小さい
4:強化を「もちもの」から行う
5:ボタンの色数が多い
基本的にどれも意図した実装にはなっていると思うのですが、ソシャゲの暗黙知というのも少なからず存在しています。
市場が出来たばかりはユーザーのメンタルモデルがなく、開発側も経験則による試行錯誤をしていたと思います。
しかし、今はある程度のメンタルモデルが形成されています。
ですので、それを利用してユーザーの学習コストを下げ、ゲームを遊ぶために必要な学習にコストを払うような設計の方が、余計なストレスなく遊びやすいのかな、と思いました。
ただ、年齢層と色数に関する事柄はもう少しちゃんと調べる必要がありそうだな、と感じました。おすすめの書籍などあれば教えて欲しいです。